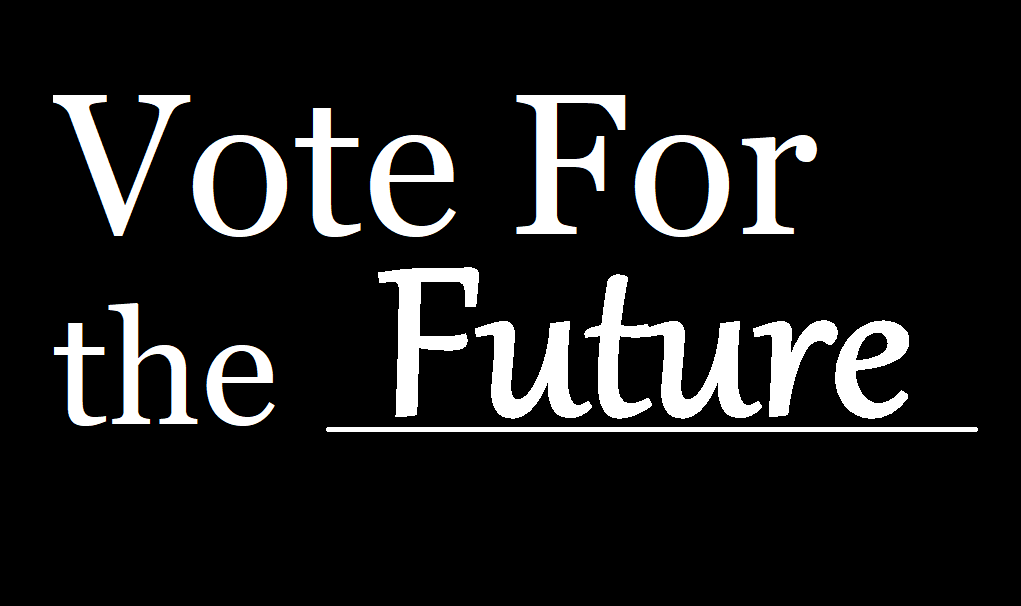「合区の」迂回?
こんにちは、akiです。
参議院選挙の投票日が迫っています。投票日は7月21日(日)です(すでに終了)。今日は、今年から新たに始まった選挙制度について解説したいと思います。
その名も「比例代表」の「特定枠」という制度です。今回の選挙は盛り上がりに欠けるとも言われていますが、この「特定枠」の違いを見るだけでも非常に興味深いものがあります。
(※2019年8月1日追記)先日の選挙以降初めての参議院が始まります。今回の選挙ではこの特定枠を利用した政党「れいわ新選組」から2人の議員が誕生しました。それにより、特定枠という制度がにわかに注目を浴びています。この結果から、一見すると特定枠の導入は「良いこと」のように思えますが、全くそうではないということを2記事にわたって解説しています。前半のこの記事では導入の経緯、そして後半の記事では野党のこの制度に対する反応と具体的に「れいわ新選組」とった戦略について書いています。
1:比例代表とは何だ?
まず、選挙には2つの投票方法があります。「選挙区」という制度と「比例代表」という制度です。
「選挙区」というのは日本を様々な地区に分けて、その中から1人または2人以上の議員を選ぶものです。今回の参議院選挙では、都道府県ごとに分けられています。
一方、「比例代表」というのは日本を地区に分けることはせず、全国から議員を選ぶことを指します。各党の獲得した票の数に応じて当選者の数が決まります。今回取り上げる「特定枠」はこちらの「比例代表」に新しく追加された制度です。
比例代表をさらに詳しく
この制度をさらに深く見ると、さらに2つのタイプに分かれます。それは「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」です。ややこしいですが、説明します。
この2つの制度の違いは「拘束」か「非拘束」かということですが、いったい何に「拘束」されているのでしょうか。それは順位です。
比例代表では、投票によって決まるのは当選者の「数」までです。実際に「誰」が当選するかは、政党が作った名簿によって決まります。そこに当選させたい人の順に「順位」を付けたのが「拘束」式、順位をつけないのが「非拘束」式なのです。参議院選挙では「非拘束」の方法が採用されています。
では、「非拘束」では順位をつけずにどうやって当選者を決めるのか?という疑問が出てきます。
それは、「名簿の中の各個人が得た票の数」です。
これもややこしいので説明します。比例代表では、「拘束」式でも「非拘束」式でも、投票用紙に政党名(「〇〇党 」)とも候補者名(「△△××」)とも書けます。
「拘束」式の場合にはどちらの投票も政党のものになり、その得票数に応じて名簿の1位から順番に当選者が決まります。一方で「非拘束」の場合には、個人名が書かれた投票はその候補者個人のものになります。当選者は個人名で書かれた票が多かった人から順に決まります。
「拘束」と「非拘束」の融合:「特定枠」
ここまで比例代表制、とくに今回の参議院選挙で採用されている「非拘束名簿式」の説明をしました。この「非拘束式」に今回から採用されたのが「特定枠」という制度です。
「特定枠」というのはいわば、「非拘束式」の中に「拘束式」をはめ込んだ制度といえます。最初に、得票数に応じて当選者の「数」が決まります(※繰り返しますが、比例代表で私たち有権者が投票で決められるのは当選者の「数」までです)。
その次に、「非拘束式」では名簿の中の人のうち「個人名」が書かれた票の多かった人から当選者を決めていきます。「特定枠」を採用している政党では、この作業のときに「特定枠」の中に入った人が他の人より優先的に当選者として選ばれます。
つまり、「特定枠」に入った候補者は個人名の書かれた票の数が他の候補者よりも少なくても最初に当選できるという訳です。
なぜこんな制度ができたのか?
なぜこんな制度ができたのかという説明をします。
時事通信社によれば、これには「合区」の制度と深いかかわりがあります。
合区とは何だ?という方に説明します。これは冒頭で説明した2種類の選挙制度のうち「比例代表」ではなく「選挙区」にかかわりがあります。冒頭で「選挙区」の説明をしたとき、「参議院選挙では、選挙区は都道府県ごとに分けられている」と書きました。
この例外が「合区」です。具体的には、島根・鳥取と、高知・徳島の2つです。この2つの選挙区では「2つの県から1人の候補者を選ぶ」ことになります。ここで問題があります。なぜなら、もともとは別々の地域が1つになったため、もともと1人ずつ選出されていたはずの議員が競合しなければならず、どちらかは失職(落選)してしまうのです。
選挙区で戦わないのであれば比例代表ということになりますが、いままで全国区でなかった人が投票用紙に「個人名」を書いてもらうということは至難の業です。ちなみに、この島根・鳥取・高知・徳島の4県から選出されているのはすべて自民党の議員です。改めて比例代表に出たとしても、自民党では重鎮議員が先に当選するでしょうから当選することは難しいでしょう。
しかし、自民党としては自らの現職議員を失う訳にはいかないので、いわば「バイパスルート」を考える必要があったわけです。つまり、この「合区」で職を失いかねない人たちをどうやって救済(当選)させるかを考え、「特別枠」で彼らを優先的に当選させる制度を作ったということです(自民党は国会の多数派ですからこういった法案を通すことはたやすいのです)。
自民党の「特定枠」に入った2人の候補者は、事実として島根、徳島を地盤とする方となっています。「合区」にはもう片方の県である鳥取、高知の方が出馬しています。
「特定枠」の1人目は、6年前の選挙で徳島県から選出された三木 亨(みき とおる)・財務大臣政務官です。もう一人の候補者は、島根県を地盤とする衆議院議員、三浦 靖(みうら やすし)・自民党青年局次長です。前回島根県で当選した島田三郎氏は今年5月に逝去されたため、代わりに衆議院議員である三浦氏が出馬しています。
それでは、他の党の「特定枠」はどうなっているのでしょう。「自民党のための制度のはずだった「特定枠」という制度に注目!【2】」で各党のを対応を比較しました。ぜひお読みください。
<参考にしたサイト>
「【図解・政治】参院選2019・比例代表の新しい当選方法(2019年7月)」、時事ドットコムニュース、2019年7月15日閲覧、
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_election-sangiin20190704j-04-w510
「【訃報】島田三郎参議院議員の葬儀について」、自民党、2019年7月16日閲覧、
https://www.jimin.jp/news/activities/139570.html
「参議院議員選挙制度に関する公職選挙法改正の概要 」、総務省、2019年7月15日閲覧
http://www.soumu.go.jp/main_content/000566100.pdf
「盛り上がり欠く参院選、投票率50%割れも」、東洋経済オンライン、2019年7月9日、2019年7月16日閲覧、
https://toyokeizai.net/articles/-/291073?
「参院選2019 立候補者一覧」、日本経済新聞、2019年7月16日閲覧、
https://vdata.nikkei.com/election/2019/sanin/kaihyo/#/hirei/party/1
「衆議院議員 三浦靖」、衆議院議員 三浦靖 オフィシャルサイト、2019年7月16日閲覧、
https://www.miurayasushi.com/
「参議院議員 三木とおる」、三木とおる公式webサイト、2019年7月16日閲覧、https://miki-toru.jp/
※この記事は特定の候補を支援または中傷する目的で執筆されたものではありません。